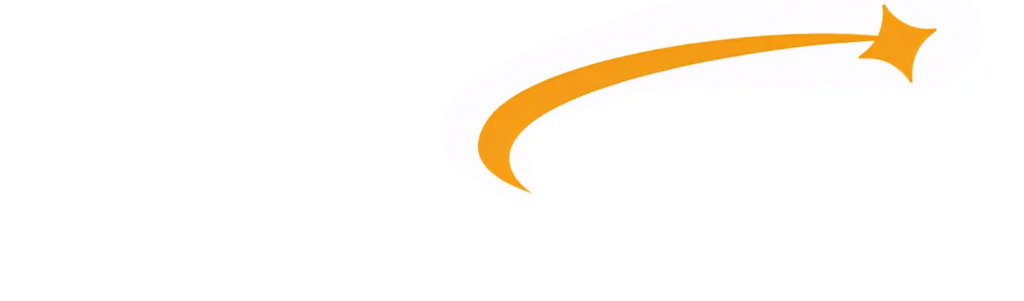こんにちは!個別指導Wit両国校です。
両国や墨田区の街を歩くと、駅前の人々の話し声、電車の走行音、川沿いの水音など、さまざまな「音」が耳に入ってきます。
実は、これらの音は私たちの身近な科学を学ぶ絶好の教材です。
今回は、両国校の個別指導Witの学びの観点から、街の音を観察しながら振動や周波数の不思議に触れる方法をご紹介します。
音って何?
まず、音の基本を押さえましょう。音は空気の振動によって生まれます。
振動が空気を伝わり、耳に届くことで私たちは音として認識します。
この振動の速さが「周波数」で、高い周波数は高い音、低い周波数は低い音として聞こえます。
例えば、両国駅のプラットフォームで電車が通過する際の「ゴーッ」という低い音と、周囲の人々の話し声の「ザワザワ」とした高い音の違いは、まさに周波数の違いによるものです。
街の音を観察してみよう
個別指導Witでは、生徒一人ひとりの学習計画に合わせて家庭学習や実験の方法も提案しています。
街歩きを科学の学習に活かすのもその一つです。まずは、両国や墨田区の街を歩きながら、聞こえる音を意識的に観察してみましょう。
- 電車やバスの走行音
- 自転車や車の通る音
- 公園の鳥の鳴き声
- 商店街の人の話し声
- 川のせせらぎや水の音
これらの音を「高い音・低い音」「大きい音・小さい音」に分類して記録します。
スマホのアプリを使って録音すると、あとで振動のパターンを視覚的に確認することも可能です。
音の高さと振動の関係
音の高さは振動の速さに関係しています。振動が速いほど音は高く、振動が遅いほど音は低くなります。
例えば、両国の商店街で聞こえる子どもの声は高く、振動が速いのが特徴です。
一方、駅前で聞こえる電車の低音は振動が遅い音です。
このように、街の音を観察するだけで、振動と周波数の関係を直感的に理解できます。
音の大きさとエネルギー
音の大きさは振動のエネルギーの大きさに比例します。
大きな声や車のエンジン音は、空気を大きく揺らすエネルギーが強いことを意味します。
両国や墨田区の街を歩きながら、静かな公園の鳥の鳴き声と、駅前の電車の音を比べてみると、振動のエネルギーの違いがよくわかります。
実験で音を感じる
家庭でも簡単な実験で振動や周波数を体験できます。
紙コップとゴムひもを使った手作りの「電話ごっこ」や、ガラスの水に指で触れて音の高さを変える実験は、振動が音にどう影響するかを楽しみながら学べます。
個別指導Witでは、こうした身近な教材を使い、学ぶ楽しさを実感できる指導も行っています。
まとめ
街の音は、私たちの身近な科学の教材です。
両国や墨田区の街中で聞こえるさまざまな音を観察することで、振動や周波数の違いを体感し、科学の原理を理解することができます。
個別指導Witでは、こうした実生活に結びついた学びも大切にしています。
次回は、観察した音を使って簡単なグラフにまとめ、周波数の違いを視覚的に学ぶ方法をご紹介します。
街歩きの学びを楽しみながら、科学への興味を広げてみましょう。