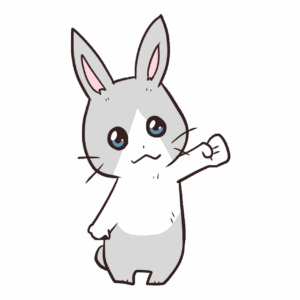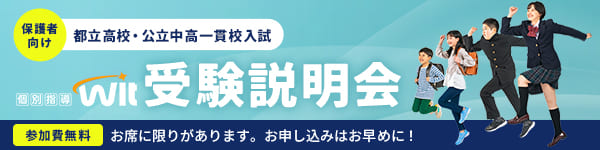こんにちは!
個別指導Witの塾長です。
前期期末テストが終わり、返却された答案を手にしたとき、多くの中学生は点数に一喜一憂してしまいます。
「思ったより取れた!」と安心する人もいれば、「勉強したのに結果が出なかった…」と落ち込む人もいるでしょう。
もちろん点数は大切ですが、それ以上に重要なのは“どのように成長できたのか”を確認することです。
テストはゴールではなく、学習の通過点。今回は、点数だけにとらわれず、次につながる振り返り方をお伝えします。
お勧め振り返り方
まず大事なのは、テスト勉強の過程を振り返ることです。
例えば、前回より勉強時間を増やせた人、苦手な教科にも挑戦できた人など、点数に表れなくても成長している部分が必ずあります。
こうした「行動の変化」を認めることは、自信を積み重ねる大切な第一歩です。
点数は外的な結果ですが、行動は自分でコントロールできます。
行動の改善が積み重なれば、必ず次のテストに反映されます。
次に、「できた問題」と「できなかった問題」を分けて考えることが重要です。
多くの生徒は「間違えたところ=できない自分」と捉えがちですが、それは違います。
できた問題は自分の努力の証拠であり、確実に力が身についている部分です。
逆に、できなかった問題は“これから伸びる余地がある部分”と考えられます。
点数に一喜一憂するよりも、両方を冷静に受け止めて「ここから先を克服すればもっと伸びる」と整理することが、学習意欲を高めるコツです。
また、成績の伸びは「点数」だけでなく「理解の深まり」にも現れます。
例えば数学で、ただ公式を当てはめるだけでなく「なぜこの式になるのか」を考えられるようになった、英語で長文を読むときに以前より内容が頭に入るようになった、理科で実験結果の意味を説明できるようになった。
こうした“学力の質的な変化”はすぐには点数に表れにくいですが、受験や将来の学びに直結する大切な成長です。
点数だけでは測れない力に目を向けることが大切です。
さらに、テスト直後は「解き直し」が最も効果的な学習になります。
間違えた問題をそのままにすると、次のテストでも同じ失敗を繰り返してしまいます。
しかし、解き直しをすれば「自分はどこでつまずいたのか」「何が理解不足なのか」がはっきりします。
例えば、計算ミスなのか、問題文を読み違えたのか、知識が不足していたのかを分類しておくと、次回の勉強法を改善できます。
この“原因分析”こそが成績を上げるカギであり、点数よりも大切な財産になります。
保護者の皆さまも、お子さまに結果を聞いたときは「何点だった?」だけでなく、「どんなことができるようになった?」「どんなところが課題だと思う?」と声をかけてみてください。子ども自身が成長を言語化できるようになると、点数に左右されずに前向きに学び続けられるようになります。
最後に、今回のテストを振り返るときにおすすめのステップをまとめます。
- 勉強の過程を振り返り、行動の変化を見つける
- できた問題とできなかった問題を分けて整理する
- 点数ではなく理解の深まりに注目する
- 解き直しで原因を分析し、次の勉強法に生かす
テストの点数は一時的な結果にすぎません。
大事なのは、その結果から何を学び、次にどうつなげるかです。
一喜一憂するよりも、自分の成長を冷静に見つめ、次のチャレンジへのエネルギーに変えていきましょう。