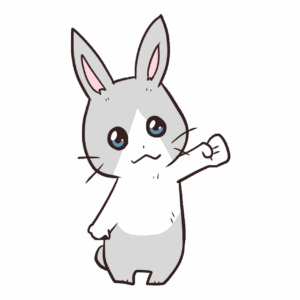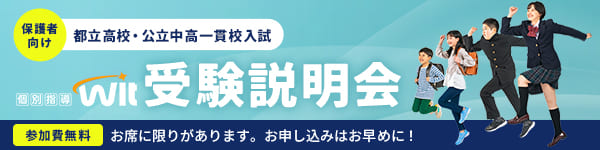前期期末テストが近づくと、多くの中学生が直面するのが「提出物ラッシュ」です。
学校ワークやプリント、課題テストの範囲……これらはテスト直前になると一気にのしかかってきます。
提出期限までに終わらせるため、夜遅くまで必死にやるという経験をした人も多いのではないでしょうか。
しかし、提出物はただ終わらせるだけではもったいないものです。
効率よく回し、テスト勉強としても最大限活用することで、成績アップにも直結します。
今回は「最短で終わらせつつ、成績にもつながる」提出物の回し方をお伝えします。
1. まずは“全体像”をつかむ
ワークやプリントを渡されたら、最初にやるべきことは「ページ数と範囲の確認」です。
これをせずに手をつけると、テスト前日に「まだ半分も終わってない!」という事態になりがちです。
具体的には、まず全ページをパラパラと見て、どれくらいの分量かを把握します。
そしてテスト日や提出日から逆算して、1日あたり何ページ進める必要があるか計算しましょう。
例)
ワーク:80ページ
提出日:テスト3日前
→ 1日15ページずつ進めると3日前に終わる計画になります。
こうして全体を見渡すことで、無理のないスケジュールを立てられます。
2. 1周目は“とにかく埋める”
ワークやプリントは、まず「1周目を早く終わらせる」ことが大切です。
この段階では丁寧に考え込みすぎず、わからない問題は空欄にせず教科書やノートを見ながらでも構いません。
目的は「全範囲を一度経験すること」です。
テスト範囲をまるごと通してやることで、どこが得意でどこが苦手かが見えてきます。
逆に、ここで完璧を目指そうとすると時間がかかりすぎ、2周目や復習に手が回らなくなります。
3. 2周目は“間違い直し”に集中
1周目が終わったら、次は間違えた問題だけを解き直します。間違いに印をつけておけば、2周目はその部分だけに集中できます。
効率の良い方法は、1周目で間違えた問題の横に赤で「×」をつけ、2周目ではそのページの「×」だけをやること。
このやり方なら、すでにできる問題には時間を使わず、苦手な部分を集中的に鍛えられます。
4. 3周目は“テスト形式”で仕上げ
仕上げは、時間を計って解く「テスト形式」です。ここでは教科書やノートを見ず、本番のつもりで取り組みます。
制限時間を設けることで、知識だけでなく「スピード」と「集中力」も鍛えられます。
テスト中の焦りや時間配分の感覚を事前に体験しておくことで、本番でも落ち着いて解けるようになります。
5. ワークを“点数アップの道具”に変える意識
提出物は「先生に出すためのもの」という意識だけだと、勉強効果が半減します。
ワークやプリントは、同じ問題がテストに出る確率が非常に高い教材です。
実際、過去に「学校ワークの問題とほぼ同じ問題がテストに出た」という生徒は少なくありません。
つまり、これらを何周も回して定着させれば、点数アップがほぼ確実に狙えるのです。
単なる「作業」にせず、「得点源」に変える意識で取り組むことが重要です。
まとめ
- 全体像をつかみ、計画を立てる
- 1周目はスピード重視で埋める
- 2周目で間違いに集中する
- 3周目はテスト形式で仕上げる
- 提出物を“得点源”として活用する意識を持つ
この流れを意識すれば、提出物はただの宿題ではなく、テストのための最強の武器に変わります。
時間に追われるだけの提出物から卒業し、成績アップにつながる勉強法にシフトしていきましょう。